前回、好きや得意、価値観はなんとなく見えてきたが「人に届けたい価値観」(仕事の目的)がなく、消化不良に終わっていた。
あれからも探り続けていたが、ひとつ腑に落ちる感覚があったのでその過程を改めて辿ってみる。ただし結論ファーストでないことを最初に謝罪しておく。結論だけ知りたい人は最後まで飛ばしてほしい。
比喩と共視、人とのつながり
クリボーを使った突飛なイメージの比喩
僕は元々比喩表現が好きだ。
比喩によるイメージの共有に、頼りがいのようなものを感じている。恐らくは相手とどれだけの知識や感覚を共有できるのかを比喩で測っているのだと思う。
ひとつ、比喩によるイメージ共有を強く体験した例を挙げてみる。友人A,Bと3人で会話していたときだ。
意味を尋ねてみると、Aは「雑魚にモテること」とだけ返した。いまいちピンとこなかったのだが、そのとき横にいたBがすかさず「クリボーに囲まれるみたいなこと?」と挟んできた。マリオとその周囲に群がる複数体のクリボーが頭に浮かび、僕もAも思わず笑ってしまったのを覚えている。
この比喩が面白いかどうかはさておき、このとき3人の頭には似たような映像が浮かんでいたはずだ。囲まれているのがマリオなのか、どのステージなのか、何体のクリボーなのか違いはあれど「人が複数のクリボーに囲まれる」という絵面は共有されていたように思う。
僕はこの感覚が好きだ。比喩によってイメージを共有する感覚。横に並んで同じものを見ているような感覚。それが好きだ。
「共視」との出会い
調べてみると、これが発達心理学の文脈で「共視」と呼ばれている概念に近いことがわかった。
この文脈では、共視の対象は現実にあるもの、目の前にあるものではあるが、それを概念にまで拡張すれば僕の持つ比喩のイメージと近しいと感じた。実際、共視は母子関係にとどまらず、他人とのつながりを感じられる概念でもあるらしい。
孫引きで大変申し訳ないが、以下は『共視論: 母子像の心理学』(北山 修 編)(2005)にて引用されていた一節である。
正面から向き合ってお互いを見つめることよりも、ふたり並んで同じ方向に視線を向け、同じひとつの対象を瞳でまさぐることが、より直接的な交感の瞬間を形作る
蓮實重彦(1983). 監督小津安二郎 ちくま学芸文庫
僕はどうやら、イメージの共有による交感の瞬間、その確かなつながりを好ましく思っていたらしい。誰かと一緒に在りたい、同じ場を共有していたいというのが僕の潜在的な欲求なのかもしれない。
ただ一方で、それが生きる理由か、それを他人に届けたいかと言われるとどうにもしっくりこない。文字通り「腑に落ちない」。喉に引っかかるのである。
そのとき頭に浮かんだのは「好き」の分野であるナレーション・朗読のことだった。
VPは微妙だが、動画のナレーションやバラエティナレーションなどは、視聴者に番組を説明する立場であると同時に、視聴者と番組を共視している立場だと思っているからだ。
視聴者の隣に並んで寄り添いながら、しかし分かりやすいように説明する。ナレーションは視聴者と番組をつなぐ場のような存在なのではないだろうか。
心を、身体感覚を、自分を味わいたい
読むことが好きである。
かつては役者や声優に憧れたこともあったが、芝居をしたり掛け合いをすることよりも、文字を声に出して読むことが好きだ。
原稿を読みながら想像した世界観を構築していく作業。
自分の息と声を感じながら、想像の中と表出した世界観とを即興で擦り合わせていく緊迫した作業。このある種のストレスを味わっているときはとても気持ちがいい。なんというか脳が痺れる感覚があるのだ。ただの酸欠かもしれない。
この脳の痺れを感じるとき、僕自身は「読むことを味わっているなあ」と感じている。
と思いを馳せたところで、ふと”味わう”ことに焦点が向いた。もしや僕は他の好きなことも”味わいたくて”やっているのではないだろうか。
コンテンツ自体はもちろんだが、それに触れているときの心や身体感覚を味わいたがっているのではないのか。
例えば、数独や論理パズルが好きだ。
解いている途中の、一つひとつがカチッカチッとはまっていく快感が好きだ。
Quantum Protocolというゲームが好きだ。
絶えず襲い来る敵の波の息苦しさと、それを捌いた後に来る安堵のため息と達成感が好きだ。
万年筆やボールペン、ノートが好きだ。
まさしく書き「味」が手を通じてダイレクトに感じられるのも、書くことで自分の思考が吐き出されていく感覚も好きだ。
他にもあるが、総じて「自分はこんな感覚を受けるんだ」「こんな感情になるんだ」というのが楽しいらしい。自分について気づきを得たいとか、自分自身を味わいたいとか、そんな欲求がある。
コンテンツももっと味わいたい。それを通じて自分自身の感覚も味わいたい。そんな風に思っている。
だって自分についてわかるって楽しくない?
同時に、周りの人にも自身について知ってほしいみたいな思いも確かにある。楽しいから味わってほしいと思っている自分がいる。鬱陶しいだろうから言わないけど。
土台の「つながる」と届けたい「味わう」
にはまそは、自分の中に眠る二つの価値観に出会った。すなわち「人とのつながり」と「味わうこと」である。
この二つの価値観自体は全くの無関係に思える。しかし、僕の中ではなんとなく繋がっていて、「人とのつながりがあってこそ安心していろんなものに没頭できる、味わえる」感覚になっている。
独りでいることが好きではあるが、誰ともつながっていない全くの孤独は不安らしい。周りのものや自分に存分に沈み込むために、誰かと在るというつながりの感覚が必要なのだと思う。
最終的に目指す価値観は何もかも味わい尽くすところにあるが、その土台になる人とのつながりも大事にしていきたい、そう考えられるようになった2025年2月であった。
そして同時に、周りの人にももっといろんな心の動き・身体感覚を味わってほしい。そのために、気になったコンテンツを味わい尽くしてほしいとも思い始めた2月だった。
補足:前回の価値観「自由・不干渉」について
前回やりたいこと探しをやった際、「自由・不干渉」という価値観が現れた。自分の中では主軸に近い価値観だと思っていたが、どうやら違うらしいと思えてきた。
もしかすると、人に干渉されることが多く、その反発から現れたものかもしれない。
支配性と自己満足の記事で書いた「○○したら?」は(もちろん相手との関係性に依存するが)自分にとっては「それにも気づけていないにはまそ」を指摘されているようで、攻撃的な言葉であり、蔑まれている感覚にも陥るものだった。
小中9年間ぐらいは、学校でもなじめず、家でも「お前は何もできない」と思われながら育ってきた感覚があるため、敏感になり過ぎて自分の行動にダメ出しされているように感じてしまったのかもしれない。
いち個人として尊重してほしい。そのうえでつながりたいという欲求を抱えながら、でも他人を「自分を攻撃するかもしれない人」と身構えて見てしまっているからこそ表れた価値観だったように思う。



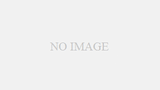
コメント
はじめまして、もかと申します。
記事を拝見しました。
私も同じINFPだからか、共感することばかりで非常にためになりました!
私自身もまさにやりたい事を探している途中ですが、筆者様のような自分の思考のアウトプットは全然甘いなと痛感しました。
(やりたい事探しの一環で、2ヵ月前にブログを開設しましたが、思うようにいかず悩んでいたところでした)
これからも記事読ませていただきます、ありがとうございました!
もかさん
コメントありがとうございます!まだ思考がまとまっていないところも多いですがそう言っていただけて嬉しいです。
やりたいこと、中々思うようにいかないですよね……。私自身道半ばですが、もかさんのやりたいことも上手くいくように応援しております!